材料・工具
材料
・ひのき 高さ120×幅90mm ×1
7,700円(税込)以上ご購入または店舗受取で基本送料無料
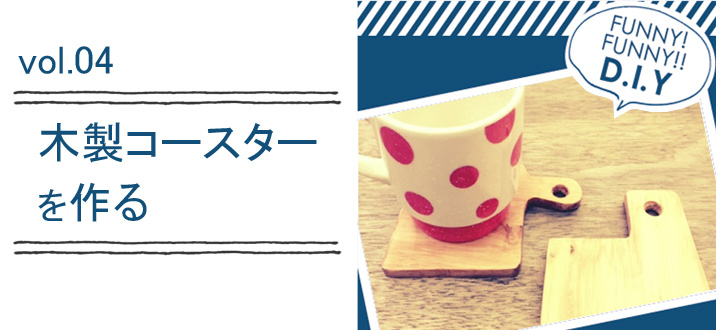
・ひのき 高さ120×幅90mm ×1
・ジグソー
・電動ドリル
・インパクトビット10mm
・クランプ
・差し金
・紙コップ
・紙やすり#150
・刷毛
・ニス
・サンダー
・ミルクペイント
※サンダーをお持ちの方は8の作業がとても楽です。詳しくは付録②へ
eショップ取り扱い商品の「ひのき 910×6×90mm」をご購入の場合は、長さ120mmにカットしていただくと、コースター7枚分と端材がとれます。
(今回使用するジグソーでカットできます。)
1. 好きなデザインを書きます。
紙コップの底や差し金などを使うと便利です。

2. クランプでしっかり固定します。

3. ジグソーでカットを行います。

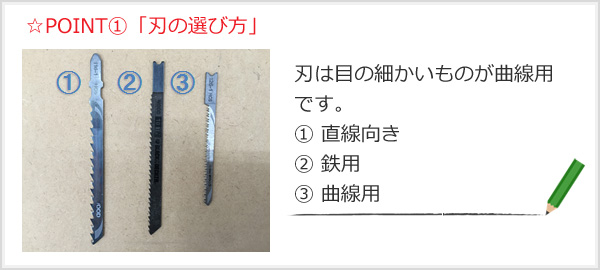
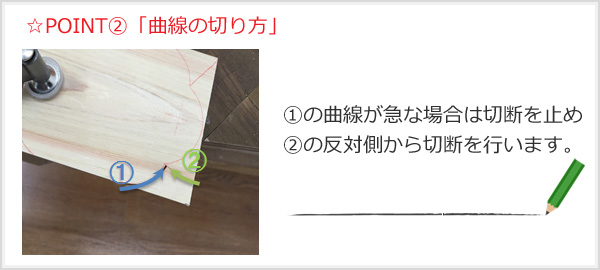
4. 曲線はジグソーをゆっくりと進めてください。

5. 穴をあける場所を決めます。
※端から8mm以上離す。(割れ防止のため)

6. ゆっくりと10mmのインパクトビットをつけた電動ドリルで穴をあけます。
非常に割れやすいので「捨て板(付録①へ)」を使って穴をあけてください。
※特に穴あけの最初は、ビットをゆっくりと回転させてください。

7. 紙やすり#150を用意します。

8. 木の目地にそって、やすりをかけていきます。
※ジグソーの切り口の多少の凸凹は、ここで滑らかにできます。

9. ニスは2回塗りを行います。乾いたら完成!

「捨て板」とは、板の端材など、穴をあけたい場所の裏側に置いて、一緒に穴をあけてしまう板のことです。
名前の通り、作品には使わない捨ててしまう板ですが、捨て板を置いて穴をあけないと、貫通時に穴の周囲の板が割れたりささくれたりしてしまいます。
私も捨て板無しで挑戦してみましたが、見事に割れました…
ジグソーで思い通りの形にカットできたのに、その後の穴あけで割れてしまうと、ショックですよね!
このひと手間が完成度に大きく関わります。
知っておきたいちょっとしたテクニック、使ってみて下さい。
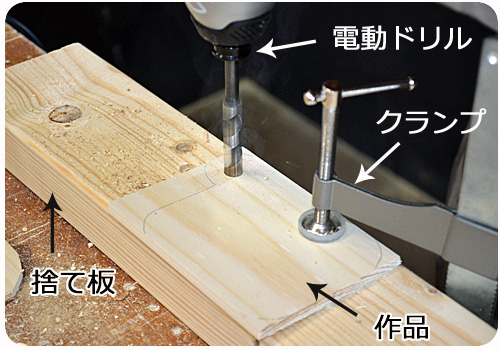
木材を加工すると面や角に貼りが発生したり、ササクレヤザラザラができます。
そのままでは使ったり塗装したりできないので、紙やすりで研磨してスベスベにしますよね。
この研磨作業、小さなものであればあまり労力はかかりませんが、研磨するスペースや数が多いと案外手間なもの。
そこで便利なのが、電動の「サンダー」!
実際に私も使ってみました!
底面に紙やすりを装着して、モーターの力で振動させることで、木材などを研磨することができる電動工具。
本体を材料に軽く押し当てて動かすことで、効率よく研磨作業が行えて、面倒な作業もあっという間です。
例えば、ジグソーで曲線をカットしたけどガタガタしてる…
角にバリができた…
という時も、大丈夫。
サンダーで軽く研磨すると、簡単にスベスベになってくれました^^
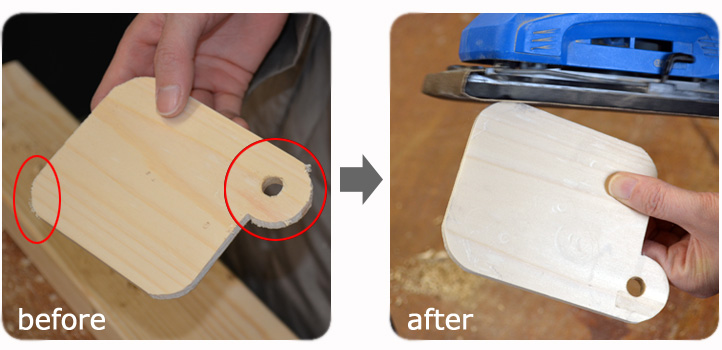
第4回「木製コースター」の作り方、いかがでしたでしょうか?
今回、『DIY初めての方も挑戦しやすい』レシピをセレクトしました。
ポイントは2つ。
①ジグソーを使ってカット
②穴あけ
私は初めてのジグソーでしたが、今回使用した木材はあまり厚くないので切りやすく、想像していたより手軽でした。
後で紙やすりで形の微調整ができるので、あまり気負わなくて大丈夫なんです!
「DIYを始めたいけど、何も持ってない!」という方も、今回必要なのは今後も使えるDIYの基本的な工具ばかりなので、おすすめです。
さて、次回は何を作りましょう?
どうぞお楽しみに♪♪
本日も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました(*^^*)
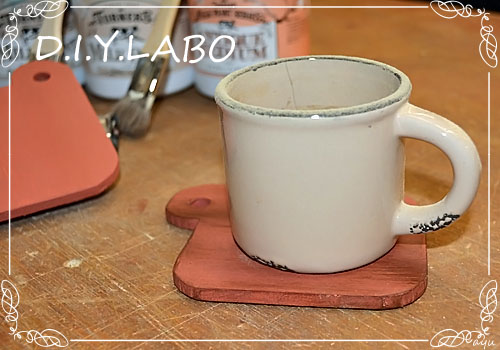
※写真中央は「ミルクペイント アンティークコーラル」で塗った後、「ミルクペイント アンティークM」で
茶色のアンティーク加工をしました。 左上は「ミルクペイント アンティークコーラル」のみ使用です。